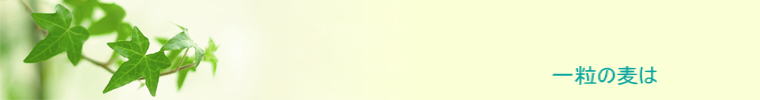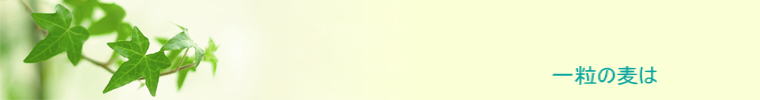| ヨハネによる福音書第12章
(20)さて、祭りのとき礼拝するためにエルサレムに上って来た人々の中に、何人かのギリシア人がいた。(21)彼らは、ガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとへ来て、「お願いです。イエスにお目にかかりたいのです」と頼んだ。(22)フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行って、イエスに話した。(23)イエスはこうお答えになった。「人の子が栄光を受ける時が来た。(24)はっきり言っておく。一粒の麦は、地に落ちて死ななければ、一粒のままである。だが、死ねば、多くの実を結ぶ。(25)自分の命を愛する者は、それを失うが、この世で自分の命を憎む人は、それを保って永遠の命に至る。(26)わたしに仕えようとする者は、わたしに従え。そうすれば、わたしのいるところに、わたしに仕える者もいることになる。わたしに仕える者がいれば、父はその人を大切にしてくださる。」
◆一粒の麦は(『生きること』の問い)この世界がどういう姿をしているか。本当の自分に出会う道
本日は、一粒の麦の話しを通して人が「生きること」とは、どういうことなのかを探りたいと思います。この教会のユーワン先生は、大阪教区報に「宗教と科学」という記事を書いておられました。科学者のアインシュタインは「宗教のない科学は不完全であり、科学のない宗教は盲目である(Science
without religion is lame, religion without science is blind.)」と言いました。確かに、人間は人類を滅ぼすことができるような核兵器を造り、人間がコントロールできないような原子力発電所、福島、チェルノブイリなどを造ってしまいます。最近の話題では人工知能AIが自動車の自動運転をするようになりましたが、一方で手のひらにのる何百ものAIを搭載したドローンを一斉に飛ばし、人間の命を狙う兵器として用いられようとしています、さらに遺伝子を操作し人を改造する技術も手に入れました。しかし、人間の側に立たない、人を物のように扱う科学は不完全だといえます。
一方で、宗教は、個人の将来を預言したり、誰も見たことのない死後の世界のことを科学的な根拠もなく宗教勧誘の手段に利用することがあります。また、震災を神の怒り、事故死を人の罪のせいにするなど、宗教の教えとは言えない、人の不安を逆手に取ることもあります。キリスト教でも、復活を生き返ること、蘇生することと考えることがあります。又、神の国や永遠の命を個人の心の問題にしたり、死んでから出会える不思議なことと考えたりと、勝手に解釈することがあります。今でも、宗教は、科学と対立するのだから宗教が科学的ではないこともやむを得ないと考える人もいます。コレでは現代社会の若い人が教会に来ることはありません。
若い人は、生きることの意味を考えなくなり、楽しく過ごせればそれで良い、と考えているのかもしれません。パウロは、このことを「食べたり飲んだりしようではないか。どうせ明日は死ぬ身ではないかと言うことになる(1コリ15:32)」と揶揄します。若者は、生きるとはどのようなことだと考えているのでしょうか。不安はないのでしょうか。
本日読まれました福音書には「ギリシャ人、イエスに会いに来る」という小見出しを付けています。もちろん原文にはこのような小見出しも、12章20節というような区分もありません。第2次世界戦争後発見されたイエス時代の資料を含む死海文書発見のおかげで聖書学という学問が急速に発展しました。人文科学のおかげで便利になりました。
イエスが生まれた時代のイスラエル社会の宗教は、今から3400年前、紀元前1400年に始まったと言われます。紙やペンがない時代にこの時代の記録は、どのようにして保存されたのでしょうか。それは祈りや詩の中に組み込まれ伝承されたのです。一番古い伝承は、その年の最初の収穫物を神様に献げるときこのように祈りなさいと言われ、それが言葉で人々の間で伝承されてきたものです。申命記26章には『(5)あなたはあなたの神、主の前で次のように告白しなさい。「わたしの先祖は、滅びゆく一アラム人であり、わずかな人を伴ってエジプトに下り、そこに寄留しました。しかしそこで、強くて数の多い、大いなる国民になりました。(6)エジプト人はこのわたしたちを虐げ、苦しめ、重労働を課しました。(7)わたしたちが先祖の神、主に助けを求めると、主はわたしたちの声を聞き、わたしたちの受けた苦しみと労苦と虐げを御覧になり、(8)力ある御手と御腕を伸ばし、大いなる恐るべきこととしるしと奇跡をもってわたしたちをエジプトから導き出し、(9)この所に導き入れて乳と蜜の流れるこの土地を与えられました。(26:5」』とあります。又、当時の様子を歌われてきた歌が、詩編の中に多く残っています。紀元前6世紀のバビロン捕囚の時代に聖書として編纂されました、他国に移住した人、現代で言う難民や社会的に小さくされた人、弱者と共にいてくれる神です。この神とともに律法を守って生活していました。
これに対してイエスの時代のギリシャの様子はどのようだったでしょうか。パウロがアテネのアレオパゴスの丘で宣教したときのことです。使徒言行録の17章で、パウロは次のように切り出します。「アテネの皆さん、あらゆる点においてあなたがたが信仰のあつい方であることを、わたしは認めます。(23)道を歩きながら、あなたがたが拝むいろいろなものを見ていると、『知られざる神に』と刻まれている祭壇さえ見つけたからです。それで、あなたがたが知らずに拝んでいるもの、それをわたしはお知らせしましょう。(24)世界とその中の万物とを造られた神が、その方です。この神は天地の主ですから、手で造った神殿などにはお住みになりません。(25)また、何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。すべての人に命と息と、その他すべてのものを与えてくださるのは、この神だからです。」このように切り出しました。無宗教の日本人にも言いたい言葉です。
ヘブライ文化に対して、ギリシャ人のヘレニズム文化はあらゆるものを超える大いなる唯一の神を知りません。一神教の神をギリシャ人にも分かるようにと話された言葉が、本日の聖書のイエスの言葉です。本日読まれましたヨハネの福音書は、共通の資料に基づいて書かれた共観福音書と呼ばれるマタイ、マルコ、ルカとは違い、一番遅く1世紀末に書かれた福音書です。録音テープが残っていないのでイエスがこのよな「一粒の麦」の話しをしたのかどうか分かりません。たぶん、ある意味で哲学的とも言えるこのようなことは言ってはいないでしょう。しかし、後の時代の人が、イエスがこのようなことを言っていたに違いないと考えることは、イエスの行動から十分理解できます。私たちは行動からしか、人の考えていることは分からないのです。
本日の福音書24節で、イエスは、『一粒の麦は、地に落ちて死ななければ、一粒のままである。だが、死ねば、多くの実を結ぶ。』と言います。この言葉は、人間はこの世に生まれてきて自分を捨てなければ、自分を大切にすれば一粒のままである。だが、自分を捨てて他人を大切にすれば、多くの実を結ぶ。」と言っているとも言えます。自分を犠牲にして他人を大切にしなさいと言っているわけではありません。しかし、少なくとも、信仰が、個人の心の問題だと言っているのではないことは明らかです。
それでは、自分を捨てるとはどのようなことでしょう。ギリシャに戻ります。現代のギリシャは、古代文化の中心地だったギリシャではなく、経済の破綻を経験し、若者の半数は失業中です。それにギリシャにたどり着いた中東やアフリカからの難民は、EUとトルコの協定によって、トルコからの流入は止まりましたが、ギリシャに着いた難民は北のヨーロッパに向けて動きだすことが出来ず、ギリシャの島々や港の埠頭に留まっています。「国境なき医師団(Medecins Sans Frontieres)を見に行くと」言う本の中で伊藤せいこうさんが書いています。MSFの人たちが難民の世話をしている様子を詳しく、自分の思いも込めて書かれた本です。
港の難民キャンプのテントから出てきた黒いアラブのザックリとした服を着た親子3人は普通の身なりの家族です。体調を崩したのでしょうか女性、母親が診察室に入ります。父親と子供が残って外で待っています。スタッフは、すかさず自分たちが座っていた椅子を二人に差し出します。この親子は、紛争による混乱がなければ今も平穏に自分の家で暮らしていたのでしょう。本の著者は、スタッフや難民の振る舞いを見て「難民は俺だ」「明日、俺が彼らのようになっても不思議ではないのだ」と直感します。スタッフが難民たちに対して敬意、尊敬の心を持って大切にしている理由が分かります。それらの対応は単なる同情ではありません。共感する、気持ちを同じくする。思いやりです。他人を自分としてとらえ、自分を他人としてしまうのです。さらに、小さい島の仮設住宅の広場で女の子が遊んでいるのを見て、聞きます。「将来どうしたい。」「弁護士かお医者さん。」少女は自分の助けてもらった経験からそう言うのです。また、トルコからギリシャに渡るゴムボートで夫を亡くした女性は、沢山の紙コップに紅茶を注いでいます。そして言います「将来は人の役に立つ仕事をしたい」彼女は多くの難民のひとときの息抜きのために紅茶を入れていたのです。難民でありながら彼女たちは、私たちと同じ思いなのです。「たまたま彼らだった私」「たまたま私だった彼ら」という視点から見ると、私たちの暮らし、生活さらには生活してきた歴史と地域、言い換えれば、時と空間を超えて人々はどのようにして、命を引き継ぎ、今の状態になっているのかを知ることになるのです。このような視点から「私はあなたたちだ、あなたたちは私だ」みんな同じ命を生きるものだ。私たちはこのように生かされているのだと知ることが出来ます。この世界がどういう姿をしているかを知ることになるのです。
自分は、絶対的な存在ではない、限りある小さな存在である。大いなるもの、神様に畏怖を持って、恐れおののいて向き合って生きること、さらに、人々と不可分な、分けることが出来ない関係こそ自分なのだ。自分の生きる意味なのだと知ることが大切です。
私は、18年前に、本田哲郎神父の「サービスを提供する側にではなく、サービスを受けなければならない側に主(神様)はおられる」という言葉を知りました。私の側に神様がいるのなら、恥ずかしくて釜ヶ崎には行けません。しかし、神様は釜ヶ崎で生活する人々の側にいると言うのです。私だって釜ヶ崎に行けると思いました。
釜ヶ崎には今も500人の野宿者がいます。300人は体育館にパイプの2段ベットを敷き詰めたシェルターと呼ばれる場所で寝ます。200人は野外です。夜回りで出会うのは100人ほどです。時々、社会勉強を兼ねて夜回りボランティアに来る人がいます。尊い心だしの人々です。皆様も是非体験されてみればどうでしょうか。おにぎりやカイロを渡し、時には毛布を着せてあげます。夜回りが終わると、かわいそうで哀れな人に良いことをしたという満足感でいっぱいです。
しかし、釜ヶ崎で育った女性のスタッフは言います。「ボランティアの人たちは野宿するのを助けているようや。誰も野宿なんかしたくない。大切なのは病気ではないかと身体の調子を聞き、親しくなって野宿から脱出する方法を共に考えること違うん」と言います。逆に、野宿から脱出してアパートの住むようになった人が、夜回りを手伝ってくれることがあります。私たちにとって心強い限りです。父親の分からない大工の子として育ったイエスも、苦しんでいる人にと共にいて十字架に死んだのです。私たちにとってその生き方がどんなに心強いことでしょう。
野宿をする人は私だ、私が野宿する人だ。このように考えるとき、「自分を大切にすれば一粒のままである。だが、自分を捨てて他人を大切にすれば、多くの実を結ぶ。」というイエスの言葉が分かりやすくなります。私から人々を見るのではなく、人々の中から、人々の中で私を見るのです。自分は他人を尊重することによって自分として存在するのです。私を捨てて初めて見える世界です。私を捨てなければ、自己中心では分からない、人が生きる意味です。
イエスは、さらにヨハネの15章12節で「自分の命を捨てる」ことについてこう言います。「 (12)わたしがあなたがたを愛したように、互いに愛し合いなさい。これがわたしの掟である。(13)友のために自分の命を捨てること、(言い換えれば、自分を捨てて、自分も友達の仲間一人になりきること)これ以上に大きな愛はない。(14)わたしの命じることを行うならば、あなたがたはわたしの友である。父から聞いたことをすべてあなたがたに知らせたからである。(言い換えれば、神様の思いを私イエスの行動によってあなた方に示した)(16)あなたがたがわたしを選んだのではない。わたしがあなたがたを選んだ。あなたがたが出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、わたしがあなたがたを任命したのである。(17)互いに愛し合いなさい。これがわたしの命令である。」と言っています。
フランシスコ教皇は、教会から外に出かけて行くことを勧めます。「すべての命を守るために」というスローガンのもとに、教皇でありながら夜に抜け出して枢機卿のときに関わった路上生活者の所へ行きます。さらに、ご自身はキリスト教を超えてイスラムや仏教との対話に励んでおられます。「自分(中心)の外へ出ること」(*注1)、他者の中に出て行くことを求めています。
本日の福音書の後半を味わいたいと思います。「(25)自分の命を愛する者は、それを失うが、この世で自分の命を憎む人は、それを保って永遠の命に至る。(26)わたしに仕えようとする者は、わたしに従え。そうすれば、わたしのいるところに、わたしに仕える者もいることになる。わたしに仕える者がいれば、父はその人を大切にしてくださる。」とイエスは言います。神の国、永遠の命がどのようなものであるかを暗示しているようです。
信仰とは「一度しかない自分の人生をどのように生きるかについて確信を与えてくれるもの」です。宗教を信じる人は、一神教は、自分を限りあるもの、弱いものと認め、絶対的な、人間の考えを超えた存在(おおいなるもの)神様を見つけそれに従って生きます。神様の思いを知っていた神の子イエスの行いを行って生活します。
宗教はたいていの場合、同じように人生をどのように生きるかを探す人々の中で、人間社会の中で、自分を捨てて他人の中で愛に生きることを教えます。キリスト教の愛はこの愛です。日本では慈悲深い人とか無慈悲な人という時に使う慈悲は仏教の根本思想です(*注2)。自分と他人は別々のものではない 。(4字熟語で自分と他人は2つではない自他不二と言います)これが、慈悲の中心です。宗教は、日々の生活をこの確信を持って生きることを教えます。このような確信を持って生きることを教えてくれたことに対して感謝し賛美する場所が教会です。私たちは、聖餐ミサを受けイエスの行いを確認し、世の中でイエスの行いを行うため日曜日に集まります。
祈ります。 平和の源である神よ、あなたは、だれよりも先に、この世界にかけ寄り、一人ひとりの人間の尊厳のために人を愛し、平和を実現するためにその生涯を歩まれました。 その思いに動かされ、その道こそが本当の人々の救いに至る道、平和の道だとわたしたちも信じ、小さな力ですが、ここに集まり、ともに考え、ともに祈っています。どうぞ小さなわたしたち一人ひとりを祝福し、この世界のすべての人が互いに愛し合う関係へと、神さまの国の実現のためにと派遣してくださいますように。すべての人があなたの永遠の命に預かることができますように。特にこの世界に、苦しむ人々、悲しむ人々の上に、あなたの大いなる恵みを与えてくださいますように。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン(2019/12/9テモテ朝祷会)
(*注1)「幸福」と「人生の意味」について 教皇フランシスコ著、安齋奈津子訳
(*注2)中村元『慈悲』。最澄「忘己利他」比叡山の開祖、法然・親鸞・道元など日本仏教の出発地。
勧話から1年半経った後に朝日新聞「折々のことば」欄にこんな記事が掲載されました。 |