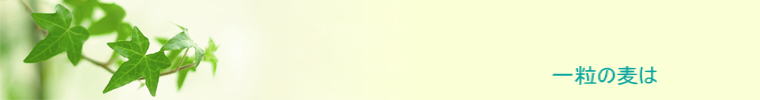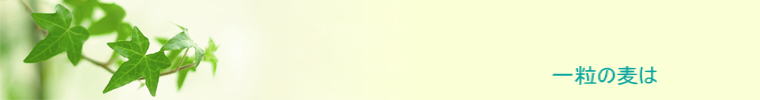| 人の子イエスは |
マタイによる福音書第13章24−43節 浜寺朝祷会 2017/12/11 堺聖テモテ教会
今日は天の国の話をしたいと思います。
朗読していただきました「天の国」のたとえ話は、たとえで注意を示されながら、小さな種「からし種}が育つところの話でした。
読まれましたマタイの福音書では「天の国」とありましたが、ほかの3つの福音書は同じことをを神の国といっています。
日本では、天の国、神の国といいますと、仏教の影響でしょうか、極楽浄土、死でから行くところ、生きていた地上のような苦しみがないところを思い描く人も多いかと思います。
イエスが世に出て、公に現れて洗礼を受け、宣教の最初にいった言葉は有名です。「時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい」と言われた(マルコ1:15)のです。イエスは、神の国を宣べ伝えるために世に来たのです。
私たちは、イエスが教えられた祈り、主の祈りで、み国が「来ますように」と祈ります。決して、死んでからみ国へ「行けますように」とは祈りません。神の国は、死んでから行くところではなく、生きていて実現させる神様の思いが実現する国です。この神の国は目に見えません。しかも、「み心が天に行われるとおり地にも行われますように」と祈っているにもかかわらず、私たちは神様がどのような思いでおられるのかを知ることができません。
神の国や神様の思いが分からないない私たちに、イエスは、具体的に、その行動、行いのすべてをもって示してくださいました。神の子イエスだけが、私たちに見える形で神の国、神様の思いを示すことができたのです。逆かもしれません。イエスの行いが、神様の思う神の国を示していたので神様がイエスを神の子としたのでしょう。イエスが十字架で死んだ後に、神様は、イエスの行いを知る弟子たちに、幻のうちに現れ、「イエスは、その生涯をかけた行いで、わたしの思いを示した。そして、よみがえった」と知らせたのです。復活とはこのことを言います。
カトリックや聖公会が、日曜毎に、日課に基づき、福音書からイエスの行いに思い巡らすのは、イエスが教え、実践した行いを知り神様の思いが実現する国を知るためです。神の国の具体的な姿が現れているからです。わたしは、イエスの出てこない説教は説教ではないとも教えられもしました。
では、イエスは、神の国を知らせるためにどこで居たのでしょうか。
イエスが生きた現場はどこだったでしょうか。困難な状況の中で、苦しむ人の所です。マルコの福音書には、イエスが来たことを「医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく病人である。わたしが来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。」(マルコ2:17)とあります。
またマタイの福音書11章ではローマの役人に捕らえられた洗礼者ヨハネが牢屋の中で、イエスのなさったことを聞き、自分の弟子たちをイエスのもとにを送ると、イエスは、こうお答えになりました。「行って、見聞きしていることを洗礼者ヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。」この記事は奇跡を行っていたと言うことに重点があるのではなく、誰の所に行っていたのか、どこに行っていたのか、誰に寄り添っていたのかを示しています。イエスは、世の中に神様の思いを実現するために、言い換えれば、神の国を私たちに教えるために、困難を抱え苦しむ人と共にいて、「大丈夫だよ」と言っていたのです。苦しんでいた人々はどれほど勇気づけられ、喜んだことでしょう。逆に言えば、困難な状況にある人々への徹底した寄り添いが奇跡に見えたのかもしれません。イエスはその生い立ちから苦しむ人の痛みを知り、苦しむ人の側にいたのです。その神は、昔、イスラエルの民が奴隷となってエジプトにいたときから虐げられ傷ついている人々を顧みられる、イエスの時代の人々もよく知っていた神です。
わたしが神学校で日本の教会論の一人者であられる上智大学のイエズス会司祭、岩島忠彦先生の話を聞いたことがあります。先生は、教会論を始める前にフランスの神学者のアルフレート・ロワジーの言葉を引用しました。それは、「イエスは神の国を予告したが、到来したのは教会であった」と言う言葉です。わたしは、教会からイエスを見ていましたが、この言葉は逆に、イエスの側から教会を見ているのです。見方、視点が違うのです。イエスは、教会ができるとは思ってもみませんでした。イエスは、教会を知りません。
これから神学の勉強ををしようとしていたわたしは、この言葉に衝撃を受けました。岩島先生の教会論は、イエスの思い、従って神様の思いを実現する教会はどのようにあらねばならないかという問題意識のもとに講義を始めました。
イエスの行いを実行しようと苦しむ人に寄り添っていた初期のクリスチャンと呼ばれる人々の集まりは、ユダヤ教徒、さらにはローマ帝国の迫害を受けました。それでも、クリスチャンのイエスが示した神の国を求める力は大きくなり、やっと、ローマ帝国から認められて教会できあがっりました。しかし、教会とその制度は人間が作りました。西暦392年、イエスの十字架の350年以上後のことです。教会では、中世には、罪の赦しが強調され、神の恵みは免罪符に象徴されるようお金と結びついたりもしました。聖地エルサレムをイスラムから奪還するために十字軍を送りました。このような教会に対して宗教改革が起こり抗議する人々プロテスタントができました。ルターが95箇条の誓文を発表して今年の10月でちょうど500年になりました。人の自由、心の自由が強調されました。今、教会といえば建物やステンドグラス、賛美歌であり、誕生、結婚、葬式など人生のそれぞれの節目に行われる宗教儀式であり、イエスの行いとは関係なくなっています。
カトリックでは今から半世紀前の1962から65年にかけて行われた第二バチカン公会議で、今まで個人を教会に縛リ付けていた言葉「教会の外に救いなし」から「教会の外にも救いはある」と変わりました。
現在の法王・フランシスコ教皇が、数年前の聖なる週の木曜日にローマの監獄に行き、受刑者の男性や女性、キリスト信者やイスラム信者の足を洗いました。又、最近では、キリスト教には関係ないロヒンギャ難民のために仏教の国ミャンマーとイスラム教の国バングラデシュに行きました。神の国を目指す宗教に対立があってはならないのです。長く培われた教会の体質は簡単には変われませんが、教皇自らがその変化を象徴する行いをして、教会の将来を示しているのです。神の国は、キリスト教の教派だけではなく、宗教をも超えているのかもしれません。
教会論の岩島先生は、「第二バチカンにより、カトリックが、プロテスタントの信仰内容である精神の自由、魂の平安に対しある意味で肩身の狭い思いをしていたのを、それらを踏まえ、さらに乗り越えることができた」、と言われ、喜ばれ、自信を示されました。神様によって生かされている私たちは心の内面の平安にとどまるのではなく、この世との関わりが大切だとされたのです。
話は変わりますが、もし、このまま若い人が教会に来なくなれば教会はどうなるのでしょうか。世界は神様のものであり、神様が備えてくださるから、私たちは祈っておれば良いのでしょうか。若い人たちは、自分中心の快楽、喜びを求めること、楽して生きること、それが限られた命を生きる幸福な人生だと考えています。しかし、一方、志のある若い人は、自分を楽しませる時間を犠牲にしてでも、困難に苦しむ人のもとにボランティアに出かけます。しかし、教会には来ません。わたしはそれで良いのだと思います。神様は、マタイによる福音書で「わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである。」(25:40)「しなかったのは、わたしにしてくれなかったことなのである」というのです。苦しむ人々に寄り添った若者に気づいてもらいたいのは、「自分がこの世にいる時に、同じ時代に生活をする人々が苦しんでいてはいけない」と言うことに留まらず「自分は一生懸命に生きているのではなく、人間以上のもの生かされて生きている。」と言うことです。これは、イエスが示した新しい契約、「隣人を愛せよ」であり、言い換えれば、苦しむ人を大切にすることです。このことに気づけば、教会に来なくても、それで十分ではないでしょうか。逆に、教会に来ている人が、苦しんでいる人々を無視してはなりません。
信仰を持って生きるとは、自分の生き方を、限られた知識しか持たない自分の考えで生きるのではなく、人間以上のものに教えられ、イエスの行いに教えられて、信頼して歩みを起こすこと(ヨハネ14:2)です。
神の国は、私たちの心の中に造るものではなく、私たちが生活するこの世の中、社会の中に造るものです。それが小さなからし種であってもイエスが行いによって具体的に示された、従って神様の思いに満ちたところです。
教会を造ったと言われるパウロは、ローマの信徒への手紙で、神の国は正義と平和と喜びです(ロマ14:17)、と言っています。正義も、平和も、喜びもイエスの行いを通して神様の思いを知り、苦しむ人に寄り添うことから始まります。
祈ります。 平和の源である神よ、あなたは、だれよりも先に、この世界にかけ寄り、一人ひとりの人間の尊厳のために人を愛し、平和を実現するためにその生涯を歩まれました。 その思いに動かされ、その道こそが本当の人々の救いに至る道、平和の道だとわたしたちも信じ、小さな力ですが、ここに集まり、ともに考え、ともに祈っています。どうぞ小さなわたしたち一人ひとりを祝福し、この世界のすべての人が互いに愛し合う関係へと神さまの国の実現のためにと派遣してくださいますように。すべての人があなたの永遠の命に預かることができますように。特にこの世界に、苦しむ人々、悲しむ人々の上に、あなたの大いなる恵みを与えてくださいますように。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン
この勧話の半年後、こんな新聞記事がありました。
|
|
|
|