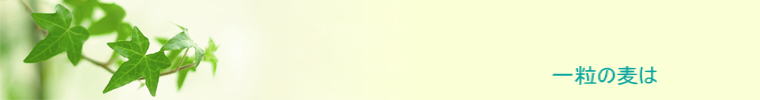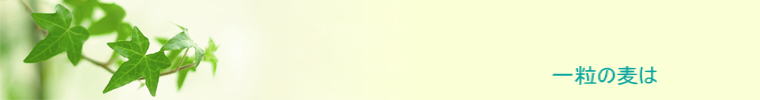| 人の子イエスは |
大阪教区婦人会 被献日礼拝 2010年2月2日 堺聖テモテ教会
ルカによる福音書2:22−40
わたしは、毎月第2と第4主日に教会でみ言葉の礼拝をするのですが、先月の17日は第3主日で私は教会での役割はありませんでした。釜ヶ崎の礼拝に出席しました。ここでの代梼は、祈りたい人が会衆席から祈ります。会衆席からは「主よ、わたしたちの願いを聞き入れてください」と応答します。シスターによって阪神淡路大震災の15周年の日と共にハイチの地震の犠牲者、被災者について祈られました。次に、炊き出しの責任者である若い人が立って、祈る前に説明しました。先週、私の母がなくなったことで皆さんにお祈りしていただきましたが、礼拝が終わった後で、ある人から「お前はいい母親がいてよかったな。ワシは母親に捨てられたんや」と言われたそうです。そう言った人は出席していなかったのですが、その若い責任者は祈りました。「自分は母親をなくした自分のことばかり思っていて、そのような人がいることに思いを至らせることができませんでした。その人がお母さんと再会できますように、また和解がなされますように」と。しかし、この責任者は、統合失調症の母親を看取ったのです。彼は最近は時々自身もおかしなことを言うようになりました。母と子の関係は本当にいろいろあるものだと思いました。
さて、わたしたちのイエスの母マリヤは、結婚してできた子が本当に結婚した相手の子供の子であるかを確認するために設定された婚約期間中に、婚約者ヨセフ以外の子を妊娠したのです。イエスは、母マリヤから父親の分からない子として生まれました。このような子がイスラエルの宗教が支配する社会で問題なく生まれることは難しいことでした。マリヤは石打ち刑に会っても不思議ではありません。しかし聖霊によって身ごもったといいますから、それでもいいよという神様からのOKが出たのです。ヨセフは随分心配しました。しかし、マリヤはしっかりと歌います。「身分の低い、この主のはしためにも、目を留めてくださったからです」(48節)。神はそのはしため、身分の低いマリアを心にかけられた。マリヤの賛歌と呼ばれるこの歌は、神は貧しい者の神であるということ、神は困難の中にある者の神であるということ、苦しみの底に沈んでいる者の神であるということ歌っています。さらに、「主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き降ろし、身分の低い者を高く引き上げ、飢えた人を良い物で満たし、富める者を空腹のまま追い返されます」(51〜53節)と続きます。
わたしたちは、こうした逆転を語る言葉を聞くと、何か不安な気持ちにさせられます。耳障りもよくないので、しばしば読みすごそうとしますが、それは許されないでしょう。これから起こる何かを暗示しているようです。本日は被献日の礼拝ですが、この日に、イエスは、両親に抱かれてエルサレムの神殿に連れて来られました。それは「主に献げるため」(22節)でありました。これはイスラエルの古くからの習慣で、最初に生まれた男の子(初子)は、主に献げられるということになっていました。その男の子の身代わりとして「山鳩一つがいか、家鳩の雛二羽をいけにえとして献げるため」(24節)と記されています。実は、これは貧しい人の献げ物でした。この時代、豊かな人々は、最初の子どもを神殿に連れて行った時には、小羊を身代わりの献げ物として献げました。ところがそれに手の届かない貧しい人は、この「山鳩一つがいか、家鳩の雛二羽」でもかまわない、とされていたのです。そのことよりも、本日の福音書の中心はシメオンの讃歌と呼ばれる箇所です。シメオンは、両親が幼子イエスをイスラエルの社会を支配する宗教が定めた掟、律法の規定通りに連れてきたのを見て、「主よ、今こそあなたは、お言葉どおりこの僕を安らかに去らせてくださいます。(30)わたしはこの目であなたの救いを見たからです。」と言います。なぜ、生まれたばかりの幼子をみて主の救いを見たのでしょうか。もしかして、貧しく父親の分からない母マリヤから生まれたイエスが、律法の通りに儀式をすることができた、あるいはすることを許された、厳しく人を差別するイスラエルの社会に受け入れられた、イスラエルの社会にはいることができたからではないでしょうか。
イエスは、成人して世に出たときに、汚れていると言ってイスラエルの社会からはじき出された重い皮膚病を患っている人を癒したときに、「行って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために献げて、人々に証明しなさい。(マルコ1:44)」とか「自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れみ、あなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。(5:19)」とイスラエルの社会に復帰するようにと言います。聖書学者はこれをイエスの「帰還命令」と言います。帰還とは、宇宙飛行士が地球へ帰ってくるときに使う、巡り帰ってくると意味の帰還です。イエスの時代に生活の悪条件が重なり、病気や障害が起こり、社会的にも、宗教的にももはや這い上がれなくなる。滅びのみが待っている。見捨てられた人々がいました。イエスは、このような社会に直面し「群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て、深く憐れまれた。(マタイ9:36)」からで、イエス自身も一歩誤ればこのような状態になっていたかもしれないのです。奇跡や癒しの後の帰還命令とは「あなたは、罪人・汚れた者という状態から、家族・社会に復帰できる状態になった」という確認の言葉を意味します。これを耳にした癒された人は、まさに死から生に蘇った思いがしたことでしょう。このようにイエスは、最下層の人々を、治療を通して、社会や家庭へ復帰させていったのです。
被献日の福音書では「親子は主の律法で定められたことをみな終えたので、自分たちの町であるガリラヤのナザレに帰った。」とあります。父母は、共に無事にイスラエルの宗教の掟、律法を守ることができたのです。
しかし、イエスは、洗礼者ヨハネの洗礼を受けて世に出ましたが、生まれ育った境遇からでしょうか、イスラエル宗教の律法だけを守る社会を批判する者として現れます。安息日をめぐる論争で「律法は何のためにあるのか」についてイエスの答えははっきりしています。「安息日は、人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。(28)だから、人の子は安息日の主でもある。」のです。宗教の掟、律法を守ることよりも貧しい人を守ることが大切であるというのです。世に出たイエスの第一声は「時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい」と言われました。これは、貧しい人が大切にされる神の国は、イスラエルの宗教の掟を、律法を、形式的に守ることによって形成される社会の中にあって、逆に守れなくてはじき出した人々の側に立ち、痛みを知り行動を起こしなさいと言うことではないでしょうか。本当に人の痛みを知るには実際に痛みを感じている人の現場に出向き同じ目線で見てみることが必要です。聖書で言う「洗礼」バプテスマというギリシャ語の言葉の意味は「一度沈んでそこから立ち上がる」ことを言います。どこに沈むのでしょうか。人の痛みが分かるとろです。悔い改めて福音を信じるとは、「絶えず痛みと苦しみを負わされている貧しい小さくされた人たちの立つ、社会の低みに立って見直しなさい」ということです。しかし、今のキリスト教では過去の自分の過ちを悪かったと反省し改めることだと理解されています。素晴らしい人柄の多いクリスチャンの中には何を悔い、何を改めるか分からなかった人が多いのではないでしょうか。逆に釜ケ崎のオッちゃんはそれがよく分かっています。何よりも仲間の病気を気にしますし、ひもじい思いでいても持っている食べ物は分かち合います。彼らは教会で洗礼を受けていませんが、社会の現場で、すでに「貧しさ」という洗礼を受けているのです。
元々、イスラエルの神は、「エジプト人はこのわたしたちを虐げ、苦しめ、重労働を課しました。(7)わたしたちが先祖の神、主に助けを求めると、主はわたしたちの声を聞き、わたしたちの受けた苦しみと労苦と虐げを御覧になり、(8)力ある御手と御腕を伸ばし、大いなる恐るべきこととしるしと奇跡をもってわたしたちをエジプトから導き出しましたという神です。イエスの教えはもっと具体的です。追いはぎに襲われ、服を奪われ、殴られ、半殺しにあった人を助けたのは、道の反対側を通り見過ごしたイスラエルの宗教を守る祭司や、レビ人ではなく、彼らが嫌っていたサマリヤ人でした。このように聖書は旧約時代から一貫して貧しく弱く虐げられている人々のたちの側にこそ神さまの力が働くことを記しています。
わたしたちは、世の中には誘惑が多くあり、悪がはびこり、罪深いからその世の中から逃れるために、個人の魂が救われるために教会に集まるのではありません。そのような世の中に神の国の福音を宣べ伝える役目を整えるために教会に来ます。マタイの福音者にある、「飢えていたときに食べさせ、のどが渇いていたときに飲ませ、旅をしていたときに宿を貸し、裸のときに着せ、病気のときに見舞い、牢にいたときに訪ねてくれた」『はっきり言っておく。わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである。』と言う言葉はよく知られています。しかし、その後ろはあまり知られていません。『はっきり言っておく。この最も小さい者の一人にしなかったのは、わたしにしてくれなかったことなのである。』。なぜこのように言うのでしょうか。わたしたちは、この世の悪からから逃れるために教会行くのではなく、この社会に神の国の福音を知らせる役目を整えるために、派遣されるために教会に行くのです。
祈ります。
平和の源である神よ、あなたは、だれよりも先に、この世界にかけ寄り、一人ひとりの人間の尊厳のために人を愛し、平和を実現するためにその生涯を歩まれました。
その思いに動かされ、その道こそが本当の人々の救いに至る道、平和の道だとわたしたちも信じ、小さな力ですが、ここに集まり、ともに考え、ともに祈っています。
どうぞ小さなわたしたち一人ひとりを祝福し、この世界のすべての人が互いに愛し合う関係へと神さまの国の実現のためにと派遣してくださいますように。
特にこの世界に、苦しむ人々、悲しむ人々の上に、あなたの大いなる恵みを与えてくださいますように。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン
|
|
|
|